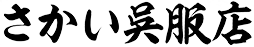初代 酒井粂次郎
東京日本橋の呉服問屋に修行に出ていた酒井粂次郎が、滋賀の(現)守山赤野井に帰ったのが明治38年でした。日本橋の問屋筋でありながら近隣に出入りの悉皆業者もいて、呉服と悉皆の両方を学べたようですが、起業するにあたり、大きな資金もなく、間違いなく生き残るには、華やかな呉服の商売よりも、悉皆業を選びました。
これは正に当家の家訓とされ続けてきた「面倒をすることで生き残れる」を守ることを地で行く生真面目粂次郎の人間性そのものでした。その悉皆の「悉 (ことごとく)」の一字をのれんに書いたのが、その年の5月8日でした。地道な仕事でしたが、当時は小袖(着物)が生活着でしたので、「悉皆の粂」の名で次第に地域に受け入れられていきました。
2代目 酒井喜市
酒井喜市が生まれたのは大正3年5月3日でした、粂次郎のこつこつと仕事をする姿「面倒をすることで生き残れる」の背中をみて家業を手伝い、二十歳になるまでには全ての仕事を任されるようになりましたが、この頃、着物といえば自家で織った手織りのものが殆どでしたが、米農家の中には、自家用米と京都の織物業者を介しての各地の品を交換入手したという、珍しい織物を悉皆に出されることがよくありました。
普段着ならば強くて薄くて光沢のある銘仙(群馬伊勢崎・埼玉秩父)や、高級な薄物なら越後(新潟)・能登(石川)・宮古上布(沖縄)、綿反ならば唐桟(千葉)・片貝(新潟)・久留米(福岡)等々といった日常着の着物でありました。
喜市は、もっと全国の産地の生地織物を見たい触れたいという気持ちに駆られました。当時、呉服の市(全国の着物 帯類を集めてくる仲買人が値をつけて捌く所)を手掛けていた友人の、(現)湖南市石部町の奥野氏(奥野商店)を手伝うことで、それはそれは多くを見て触れて知ることが出来ました。
喜市は奥野商店までの約15キロの距離を、いつも小さい自転車で懸命に付いてきた越慈(当時6歳の頃)に強いて褒めはしませんでしたが、三男である越慈の身の回りにいつも呉服がある環境を作りました。
そして、喜市は40才台半ばには、奥野商店での経験を活かして京都室町でも八木氏(丸八株式会社)・牧浦氏(株式会社とくや)らと共に各市にも顔を出して目を肥やしました。
その間も家の悉皆の仕事を朝と夕に済ませ、赤野井郵便局外交員として働きながらも、いつか呉服の店を出すという将来の夢を持っていました。
そして長年に培った信頼と社交性に富んだ性格の喜市に、悉皆だけでなく呉服業も商うようにと、室町問屋と当時の多くのお客様が後押しして下さり、悉皆に呉服を併せ持つ「さかい京染悉皆店」の看板を掲げました。
喜市50才には、守山地域内外に広くご贔屓いただくようになっていました。
3代目 酒井越慈

三代目の現店主越慈が、京都室町の呉服問屋(株式会社とくや)に勤めて守山に戻りましたのが昭和52年6月でした、しかし、小売り業を継ぐには問屋修行では知識・技能が足りないため、先代喜市の友人でもあり呉服小売業者でもある大津市桜野町の「きのした商店」に入社しましたことで、呉服の「悉 (ことごとく)」を習得できました。その商店では裏地などの生地をカットするのに、鋏はありましたが「物差し」は普段置いていませんでした。物差しが無くとも生地のカットができるようになれたのも、これはこれで生涯の大きな収穫の一つでした。
その後「さかい呉服店」を継承しましたが。悉皆のほとんどを自店工房で仕上げるようになったのはその数年後でした、幼いころから喜市の所作をみてきたことを思い出し、洗い・しみ抜き技術を独学で習得しました。そしてシミ抜きの最新超音波技術を擁した機械を福井県から導入したのでした。
花緒挿げの技術を身に付けたのは、自身が京都市内の横断歩道を急ぎ足で渡っていた時、雪駄の鼻緒が切れたのでした。それも近くを歩いていた方々にも聞こえる「ブチッ!」という音でした。七条通り大宮の履き物屋さんに助けを求め、対応してくれたのがお店のおばあちゃんでした。そして「あんた(あなた)さん、鼻緒の中に通してある紐が、麻やったさかいに麻紐が切れて捻挫せんと助かったんでっせ」と教えていただいて、草履の鼻緒に惹かれたのでした。以来、あらためて周囲をみると、履物専門店を身近に見かけなくなり、購入すれど花緒の調整・取り替え・修理が必ず必要になるはずが、履物専門店が減り、着物愛好者がお困りであることをみて、草履の鼻緒挿げ技術を東京八王子にて習得して、大阪ぞうり協同組合の花緒挿げ技能士免許を取得し、このすべてのノウハウを着物の悉皆・販売・挿げに活かすことで着物の悉くを生業としています。